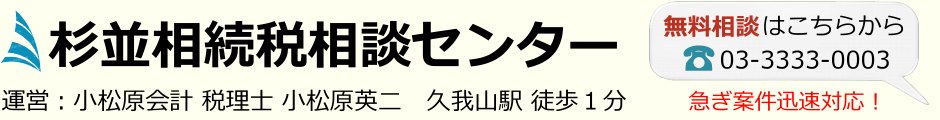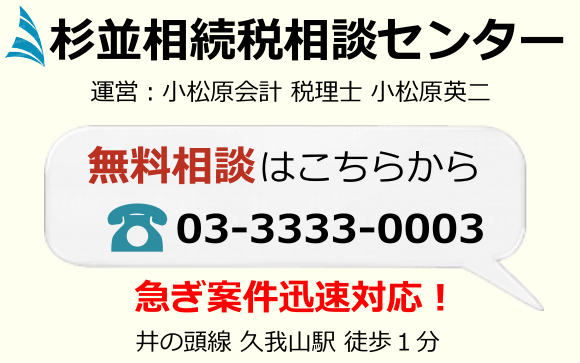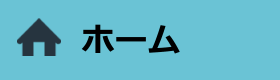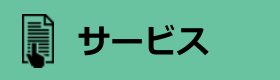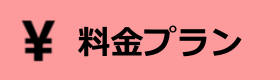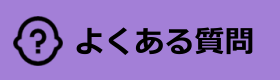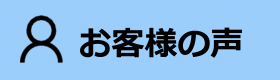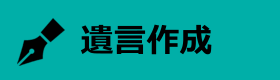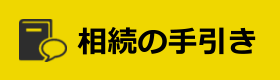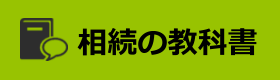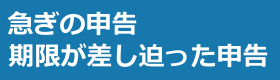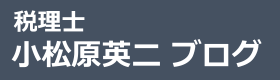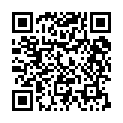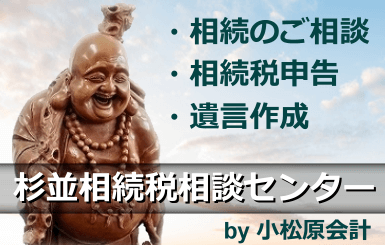遺産分割/遺産の分け方
相続人の間で、遺産をどう分けるかは基本的に自由です
遺産分割する際(相続財産を分ける際)、遺言書が存在すればそれに従うことになりますが、遺言書がない場合には、相続人全員の同意・納得のうえで自由に分けることができます。
また、法定相続分が決まっているからという理由で、これに必ず従わなければいけないわけでもありません。
法定相続分はあくまで“目安”と考えていただいてかまいません。
しかし、仮に相続人間で遺産分割について話し合いがまとまらず、調停等の争いになった場合は、この法定相続分という考え方に従うことになります。
仮に、父が亡くなったと仮定し、相続人が母(妻)と子供の2人だとすると、法定相続分は相続人それぞれ2分の1ずつですが、母(妻)が全ての財産を取得し、子供が財産を一切取得しないという遺産分割内容でも、母(妻)と子供の両者が納得していれば何の問題もないわけです。
法定相続分とは
民法が定めている各相続人の法定相続分について、主に下記の3パターンに分けられます。
- 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供1/2 - 配偶者と直系尊属(両親、祖父母等)が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属1/3 - 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
また、上記のケースで、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、その人数に応じて、均等に分けられます。
尚、上記のケースで配偶者がいない場合には、配偶者を除いた相続人の人数によって、均等の割合で相続することになります。
非嫡出子の相続分
法律上婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の法定相続分は、婚姻関係にある男女の間に生まれた子の半分となります。
つまり、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供は、そうでない子供と比べて、法定相続分が半分になるということです。
法律上婚姻関係にない男女の間に生まれた子にも、財産をきちんと相続させたい場合には、養子にすることが考えられます。
養子は子と同じに扱われますので、通常通り財産を相続できるからです。
父母のどちらかが違う兄弟姉妹の相続分
父母のどちらかが違う兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。
遺言書の内容に従いたくない場合
適法な遺言書がある場合は、基本的に遺言書の内容に従って遺産を分けなければいけません。
しかし、受遺者(遺言による財産の受取人)全員が納得すれば、遺言書を破棄し、新に相続人全員で遺産分割協議を行うことができます。
ただし、遺言による財産の受取人の中に「相続人以外」の人がいる場合に一旦遺言書を破棄してしまうと、相続人でない者は遺産分割協議に参加できないことから、その「相続人以外」の者は相続財産を取得することができなくなるので注意が必要です。

 杉並相続税相談センター
杉並相続税相談センターby 小松原会計
杉並相続税相談センター案内
運営:小松原会計事務所 税理士 小松原英二
〒168-0082 東京都杉並区久我山5-7-8
TEL:
FAX:050-3737-0297
アクセス:京王井の頭線久我山駅(急行停車駅)北口徒歩1分
- 渋谷より急行で4駅約12分
- 新宿より明大前乗換えで約17分
- 吉祥寺より急行で1駅約4分


 杉並相続税相談センター
杉並相続税相談センターby 小松原会計